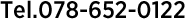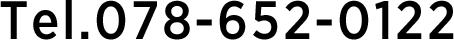Columnマイソール協会コラム
これからの療法士が考える視点 vol.6〜リハビリテーションにおける再現性〜
その他
2020.06.03
今まではコミュニケーションスキルについて書いてきました。
ここからガラッとまた方向性を変えていきます。
皆様はこんなことを経験したことはありませんか??
• 患者様へのアプローチ、同じことしているのに昨日硬かった筋肉が今日は柔らかい、あるいはその逆
• いつもと同じようなアプローチをしても入力が悪く、動作を再現できない、患者様の調子が悪い?
• 客観性の高い評価法を使用しているのに日によって点数にばらつきがあったり先輩や同僚との点数に一貫性がない
どれかはおそらく経験があるでしょう。
これらに共通していることは
「いつもと同じ」ってなに??という疑問です。
というわけで、今回は・・・
「リハビリテーションにおける再現性」について書いていきます。
基本的にはいつも同じ(ような)人に、同じかそれにかなり近い効果を出せるように!が医療の目指しているものです。
しかし、お薬などのようにある程度一定の効果が見込めるものとは違って、人と人がしていることですから、なかなか一定の!というのは難しいのでは?と思います。
そしてここは意見の分かれるところ、なんです。
EBMやEBPTなどのように前提の揃っていないものをバイアスとして除外する形であれば、セラピストによる違いは除外できる、もしくは除外すべきという意見もあることでしょう。
でも、ここでは、同じセラピストでも「非再現性」という視点でいくと毎日同じことをしても同じ結果にならないですよ、
というお話です。
ここから少し難しい表現になってしまいますが、
「再現性」という言葉は論文を書く人たちにとってはとても大切な考え方です。
他にも「妥当性」や「信頼性」など他にも大切な言葉がたくさんあります。
再現性の高い治療法を選ぶのはとても大切なことですが、リハビリテーションの世界では、先ほども書いたように同じ人に同じ治療法をしても同じ結果に繋がらないことが多々あります。
お薬のように医療の中でも反復しても再現性の比較的高いものもあれば、リハビリテーションのように再現性の低いものもある、
ということです。
お薬の世界ですら
「生物学的な理由により、生命科学研究に完全な再現性は望めない」
とAMED(日本医療研究開発機構)が述べているくらいです。
ではどうしてリハビリテーションの世界では再現性を上げることが難しいのでしょうか。
これは『ひととひと』のやり取りだから、というのが大きな理由です。
気分環境立場状況、あらゆるものがひとの身体には影響を与えます。
なので機械のようにネジを締めれば治るわけではありません。
そしてセラピストも『ひと』です。
ここも大きな再現性の低下理由です。
セラピストがもし見る角度を変えて動作の評価をしたら、恐らく評価結果が多少変化するはずです。
そしてこれについて正確な評価ではない!という人は恐らくいないかと思います。
それがいい意味でのアナログなセラピーだからです。
これに対してアナログな評価治療を全否定して「デジタル測定機器で客観的に取ればいいじゃない」
という意見が最近多くなっていています。
これは前提に再現性の高い医療を肯定している人の意見に多い印象です。
ところがここまで書いたようにリハビリテーションの世界の非再現性があります。
デジタルは一定でも、患者さまは『ひと』です。
なので非再現性が生まれます。
このように前提条件が違えば意見が食い違うため、分かり合えない形になります。
一応。デジタル測定機器を否定するつもりは全くありません。
大切なのはリハビリテーションにおける「非再現性」を理解しておくことです。
デジタルもアナログも、使い分けできる力が必要です。
目線角度を保つ、など評価の状況を一定にするためになるべく再現性の高い方法を模索することはとても大切です。
デジタル測定機器を駆使したスニーカーやインソールもたくさん出てきました。
しかし、それを扱うひとには「非再現性」があります。
そしてなにより使うユーザーの非再現性があります。
デジタルで得られた情報に命を吹き込むのはまさに「非再現性」の要素であるひとが行うのです。
一定の評価作成技術と、アナログでも「非再現性」を考慮した動作分析技術。
そして床という一定の状況。
マイソールの理論概念はそのようなデジタルとアナログを行き来するような発想で、とても素敵です。
デジタルがどれだけ普及しても、それに命を吹き込むセラピストの考え方理念技術が錆びたら意味がありません。
セラピストとして何を学ぶのか。
その評価はその測定機器は何のためにあるか。
そしてその再現性と非再現性を理解しているか。
セラピストとしてひとを磨きたいものですね。
理学療法士 森本義朗