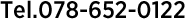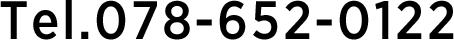Columnマイソール協会コラム
これからの療法士が考える視点 vol.3
その他
2020.02.06
これからの理学療法士に求められるスキルとして、プレゼンテーションスキル・ネゴシエーションスキルが重要、というコラムをこれまで出してきました。
プレゼンテーションスキルについてのコラムはコチラ
ネゴシエーションスキルについてのコラムはコチラ
結局のところシンプルに言うと。
コミュニケーションスキルが高いほうがいいという言うことになります。
皆さまこのようなことは経験がありませんか?
・頑張って行った評価と統合と解釈が先輩にすごく指摘されて悲しかった
・患者さんからの信用が得られない時があったけど理由がわからない
・患者さんに運動の宿題を出したもののやってくれない
・家族との喧嘩が多い
・恋人ができない
このような経験がある人はぜひコミュケーションスキルを学んで欲しいと思います。
それはリハビリ場面だけでなく生活を豊かにしますし、マイソール提案のスキルももちろん向上します。
ではコミュケーションスキルはどういうスキルでしょうか。
日本語なら日本語で話せて通じたらOK。
ではありません。
◆お互いを知り理解する。
コミュケーションを突き詰めると、
「相手のことを知り理解すること」
と
「自分のことを知って理解してもらうこと」
となります。

これらを高めるスキルが、コミュケーションスキルです。
これまでに書いてきたようなことですよね。
これで、プレゼンテーションやネゴシエーションにもつながるのが理解出来るかと思います。
◆コミュニケーションに100%の理解はない。
まずスキルという時点で「能力」ではなく「技術」です。
もちろん「能力」の下支えがあっての「技術」ですけれども、技術として磨くことができるものです。
では、どのようにそのスキルを磨けば良いでしょうか。
今までに書いたコラムにもそのヒントは多々ありますので、これらとは違う切り口を用意します。
まず、自分の話をするためにはプレゼンテーションスキルが重要でしたね。
そして、相手を知るためにネゴシエーションスキルも重要でした。
それでも100%の理解をお互いにするというのは簡単ではありません。
自分だけでもダメ、相手だけでもダメ、だからです。
構成構造主義という、
「人間科学においてありがちな信念体系どうしの対立(信念対立)を克服し、建設的なコラボレーションを促進するための方法論・思想・メタ理論のことである。」
という考え方があります。
◆大前提は互いの違いを理解すること。
大前提にある「各々の違い」を理解して関わる力がまさにコミュケーションスキルの根幹です。
少しだけ想像してみてください。
例えば今目の前にいる人と同じ場所で同じことをしている時間はどれくらいでしょう?
どれだけ親しい関係でも育ってきた環境が違います。
過ごしてきた時間は違います。
ましてや先天的要素として親も家族も違うこともあります。
逆に、過ごしてきた時間を共にしてきた人とは、「阿吽の呼吸」のようなノンバーバルなコミュケーションも出来てきますよね。
こういう互いの理解のためには時間と「各々の違い」を無意識的に理解しているからこそ出来ることです。
私たちの仕事であるリハビリテーション職は、このように大前提である「各々の違い」を理解しなければ「評価」や「統合と解釈」なんていうものは出来ません。
どれだけ客観的でメジャラブルな検査であっても、最終的に解釈するセラピストによって変わるからです。
先輩同僚後輩セラピスト間でも「統合と解釈」が変わることがありますよね?
これはまさに構成構造主義の説明中にあった「信念対立」が起きている、と言えます。
先輩だからより解釈能力が高く、新人学生だから解釈能力が低い、とは必ずしも言えない、というわけです(誤解のないように書いておきますがもちろん経験から得られたものは偉大です)。
まずは自身のコミュニケーションの現状について、自分自身を「評価」、「統合と解釈」することを必ずしてください。
それが必ず自分自身のリハビリテーションスキルをたかめるきっかけになります。
次回に、コミュニケーションスキルを高める方法について、お伝えしたいと思います。
mysole®協会理事 森本義朗